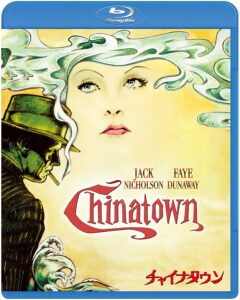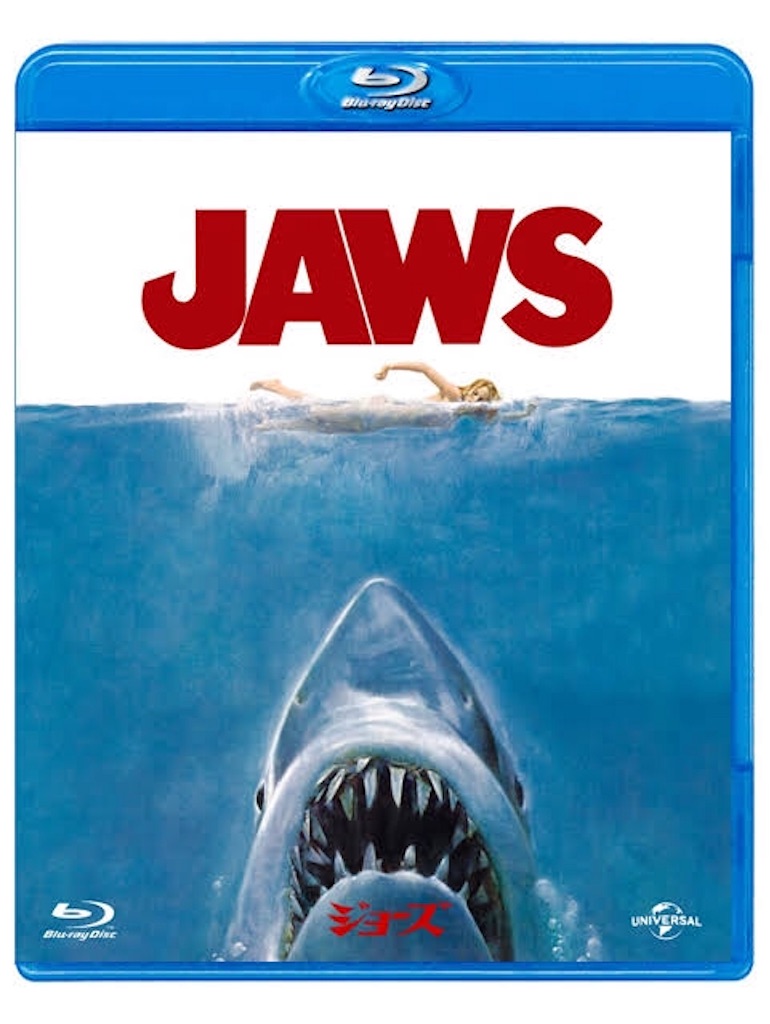
人食いザメ対3人の男たち、命がけの戦い
ジョーズ(1975年 スティーブン・スピルバーグ監督)
スピルバーグ監督の名を世界に知らしめたヒット作。本作を契機に「グリズリー」(76年)や「テンタクルズ」(77年)、「オルカ」(77年)などの動物パニック映画が量産された。筆者は本作を見てサメが怖くなり、10年間、海水浴に行かなかった。10年後、会社の慰安旅行でグアムに行ったときは最後まで波打ち際から5㍍以内の場所にいて、常に周囲をキョロキョロしていた。
ストーリーは説明の必要もないだろう。米国の観光地アミティ島に人食いザメが出現。夜間に海で泳いでいた若い女性が殺される。新任の警察署長ブロディ(ロイ・シャイダー)はビーチの封鎖を提案するが、ボーン市長は認めようとしない。そんな折、またも悲劇が起きる。今度は遊泳中の幼い少年が犠牲になったのだ。市長はサメ退治に3000ドルの賞金を出し、島は全米から詰めかけた賞金稼ぎでいっぱいになる。
そうした中、小型のサメが捕獲された。これで一件落着と思われたが、海洋学者のフーパー(リチャード・ドレイファス)はサメのアゴの長さを測り、真犯人ではないと主張。ブロディはフーパーとともにサメ捕り職人クイント(ロバート・ショー)の船で出向するのだった……。
前半は市長らのエゴ、後半はサメとの激闘の構成になっている。市長は利益を優先して現実を軽視し、犠牲者を増やしてしまう。3000ドル欲しさで集まった素人賞金稼ぎたちでごった返す港。サメの姿が見えるや、大人が子供たちを犠牲にして逃げ惑う光景など、スピルバーグ一流の皮肉が込められている。
描かれているのは行政の利益追求と安全性の対立だ。市長は市の財政を考え、書き入れ時に浜辺を閉鎖すれば稼ぎが減ると考えた。それがさらなる悲劇を生んだ。なんだか原発問題のようだ。2020年に北海道の寿都町が高レベル放射性廃棄物の最終処分場として名乗りを上げ、推進派の町長らと反対派の住民らが対立した。受け入れれば最大で20億円が入る、だけど放射能が怖いという人々のジレンマは、本作のボーン市長とブロディの対立関係に似ている。そんな人間をあざ笑うように東日本大震災で原発が白煙を上げた。福島第一原発事故は10年たったが、いまだに解決できていない。
サメも同じ。人間がカネか安全かでせめぎ合っているとき、浜辺に近づいて被害者をバリバリ食べ、悠然と去って行く。後悔先に立たず。これはサメであろうと原発であろうと手抜き工事であろうと同様である。今年7月に熱海市で起きた土石流災害は行政に責任はないのか……。
後半は海という広大な密室を舞台にした男3人の格闘劇。サメはストーカーのように人間につきまとう。森喜朗のオツムを表した「サメの脳みそ」という言葉でもわかるように、サメはかなりバカのはず。だが本作のサメはまるで人間が乗り移ったかと思うほど狡猾だ。3人が乗った小舟の周囲を音もなく旋回。撒き餌をしっかり食べて怖がらせ、体を船体にぶつけて挑発する。森喜朗より頭脳明晰かもしれない。
有名作だから、日本人のほとんどが銀幕あるいはテレビ放映で一度は見たことがあるだろうが、もし未見の人がいたら、ぜひとも鑑賞して欲しい。見て損のない作品だ。
ちなみに本作を撮ったときスピルバーグ監督は28歳だった。ウィキペディアによると、製作費900万ドルで興行収入は4億7200万ドル。日本では配給収入50億500万円。ということは日本の興行収入は100億円だろうか。
ネタバレ注意
スピルバーグは「激突!」のテクを生かして、ジワジワと恐怖を与える。序盤の沈没船探索で出現する片目をひどく損傷した死体、夜の海で小船の男たちが語り合う船の近くに突然浮上する樽と発信機の点滅、「全長8メートルだ」「いや、9メートル」という会話によるサメの巨体の迫力、ロープに足が絡まって転落しそうになる緊迫感など、実に仕掛けが細かい。フーパーが海中に下ろした檻の中からサメに水中銃を放とうとする場面ではサメを大きく見せるために小柄なスタントマンを起用したと公開当時のパンフレットに記されていた。
注目は第2次大戦中、戦艦インディアナポリス号の乗員だったクイントの回想だ。同艦はテニアン島に原爆を輸送して帰還する中、フィリピン海で日本の潜水艦から魚雷を受けて沈没。乗員1100人がサメのえじきになり、生き残ったのはクイントを含めわずか316人だった。この語りでクイントがなぜサメ退治に執念を燃やすかが判明。ロバート・ショーの薄笑いの演技によって、観客はまるで映像を見ているかのように凄惨な光景を思い浮かべることになる。
CG技術がない時代、サメの一部は張りぼてだが、海中を泳ぐ姿はなかなかの迫力もの。ラストを締めくくる紺碧の海に深紅の血柱があがる色彩のコントラストも見どころだ。三者三様の個性のぶつかる卓越したドラマ性によって、いま見ても古臭くない傑作に仕上がっている。