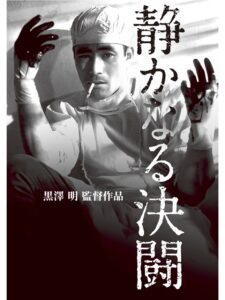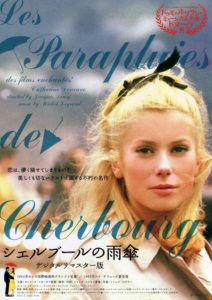「人間」と化したアンドロイドを平然と殺す捜査官
ブレード・ランナー(1982年 リドリー・スコット監督)
この「ブレードランナー」を筆者は1983年に東京・大井町の名画座のオールナイト上映で鑑賞した。同時上映は「惑星ソラリス」と「未来惑星ザルドス」だった。
本作は熱烈なファンを持つ近未来SFサスペンス。劇場公開は世界的に振るわなかったものの、その後ビデオとレーザーディスクで人気が出た。今では全世界にマニアックなファンがいて、映像とセリフを細かく観察して「ああでもない、こうでもない」と持論を述べ、議論を戦わせている。その中にはアンドロイドが最後に人間の命を救ったのはインプットされたソフトによって人間を守るようにプログラムされているからだという珍説もある。
舞台は第3次世界大戦を経た西暦2019年のロサンゼルス。人類は「レプリカント」と呼ばれるアンドロイドを地球外の奴隷労働に使っている。彼らのうち「ネクサス6型」の4体が人間を殺して地球に逃走。ロス市警のブレードランナー(捜査官)のデッカード(ハリソン・フォード)が追跡する。
デッカードはレプリを開発したタイレル博士の美人秘書レイチェル(ショーン・ヤング)と交合。実はレイチェルはレプリで、自分の正体を知らないが、デッカードとの会話で気づく。デッカードは2体のレプリを抹殺し、最後に彼らの親玉のロイ(ルトガー・ハウアー)と対決するのだった。
フィリップ・K・ディックの原作「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」と比べると、よくぞここまで改変したと呆れるほど脚色されている。おかげで映画は小説よりずっと面白い。
映画ではレプリの逃亡の目的が寿命を延ばすことになっているが、原作にそのくだりはない。原作ではレイチェルは自分がレプリであることを最初から認識しており、ロイはあっけなく殺される。デッカードは羊をペットとして飼いたいが、本物の羊は高くて手が出せない。そんな折、レプリを抹殺して報奨金3000ドルを獲得し、本物の羊を買って妻を喜ばせる。だが、その羊をレイチェルに殺されるのだ。
本作の人気が根強いのは美術とデザインの奇抜さによる。3度目の戦争で核兵器を使ったため日が差さなくなった空から酸性雨が降り続く21世紀は、白人と東洋人が行き交う人種のるつぼ。ビルには日本の芸者の映像による「強力わかもと」の電気広告だ。そんな風景をクルマが空を行きかう。饐えた匂いのする街並みと人間の体臭がハイテク技術と混然一体化している。
公開当時に「おそらく未来の空と街はこんなに汚れているのだろう」と覚悟した人もいるはずだ。リドリー・スコット監督は本作を手がける前に東京の新宿を訪れ、雑然とした雰囲気に触発されてこの絶望的な未来風景を想念したとされる。そういえば、すでに82年には新宿のスタジオアルタに大画面の動画が映し出されていた。
薄暗い都市に小柄なアジア人が行きかう光景は、混沌とした時代にはロスにアジア人が跋扈するという意味かもしれない。トランプが大統領になってからたびたびニュースで報じられた通り、82年当時の米国には非白人の人種は今ほど多くはなかったらしい。劇中のアジア人が群れていている風景は多民族国家になった現在の米国を予言していたといえるだろうか。さらにいえば、現下の新型コロナで注目を浴びた「黄禍論」を暗示しているようにも思える。
本作のレプリの位置づけは人間が作り、人間に奉仕するための「奴隷」だ。作品の冒頭で捜査官を射殺するリオン(ブライオン・ジェームズ)は放射性廃棄物の運搬を担当する労働用レプリで、女性型のプリス(ダリル・ハンナ)は慰安用だ。最後にデッカードを追い詰めるロイは戦闘用レプリと、いずれも修羅場を経験している。
これらのレプリは宇宙で反乱を起こし、人間を殺して地球に押しかけてきた。いわば獰猛な反逆者だ。だが観客の多くは殺人レプリを憎む気になれない。なぜなら彼らが「死にたくない」と苦悶しているからだ。
レプリはタイレル博士によってあらかじめ4年で死ぬように設計されていた。あくまでもアンドロイドだが、ここに計算違いが生じた。人間のように自分の意思・感情を持ち始めたのだ。つまり意思と感情が芽生えたときから、体は機械であっても「人間」になったことになる。
劇中でロイとプリスが接吻するのを見ても分かるように、彼らは恋愛感情も目覚めている。だからプリスを膝を抱いたロイはセバスチャンに「俺たちはコンピュータじゃない」と言い、プリスはその思いを「人間よ。我思う、ゆえに我あり」とデカルトの文言で補強する。こうなると「4年で死ぬのは嫌だ~」という気持ちから一日でも長く生きたいと思うのは当然だ。
そういう人間化したレプリをデッカードや彼の上司であるブライアントは職務として殺すことになる。未来版の非情のライセンスだ。デッカードは踊り子に化けたレプリのゾーラ(ジョアンナ・キャシディ)をチャイナタウンで撃ち殺した際に「いくら仕事でも女を背中から撃つのはいい気分ではなかった」と罪悪感めいたモノローグを吐くが、こうしたセリフはゾーラのときだけだ。逃げる女が次々と弾丸を浴び、無情にもショーウインドーを突き破って絶命する。筆者はデッカードのセリフを含めたゾーラの殺害場面が一番の見どころだと思う。この虚しさは感動的と表現してもいい。
ただし「ブレードランナー」にはこのモノローグが流れないバージョンもある。ファイナルカット版などにこのセリフがないのはデッカードの人間的な側面を隠すためなのだろうか。あるいはネットなどで「デッカードはハリウッド映画で女性を背後から射殺した最初の人物」と書かれるのを嫌ったのだろうか。
蛇足ながら
本作のテーマは人間化し「もっと生きたい」と望むアンドロイドとそれを退治する人間の暗闘だ。考えてみると、われわれ人間は「寿命がきたら死ぬ」という覚悟のようなものがある。殺人や事故で死んだら犯人と責任者を恨むが、病気の場合は神様が寿命を決めたのだから仕方ないと考えるものだ。神様を本気で恨んだりはしない。
日本人が過去の戦争で天皇の命令を受けて戦死しても恨まなかったのは神の命令だったからだ。神は全能だ。神は許される。そして日本人は天皇のために死ぬ。天皇による殺害を肉声にしたのはドキュメンタリー映画「靖国 YASUKUNI」(2007年 李纓監督)くらいだろう。この作品では初老の女性が「私は兄が天皇に殺されたと思う」と明言した。ただ、こうした考え方はきわめて例外的だ。戦前も戦後も、天皇は日本人にとって神聖な「現人神」「明御神(あきつみかみ)」であり、菊のタブーに守られ、批判する者は銃弾を浴びた。8月15日に九段下に行けば、右翼系の若者が「戦前のような不敬罪を導入して陛下をお守りしろ」「反天連を撃ち殺せ」と連呼している。
しかしレプリには神がいない。自分たちを作ったのはタイレル博士という人間だ。人間の都合で勝手に製造され、感情が芽生えて自分たちも人間になった。それなのに製造からわずか4年の命でまもなく死ななければならないのは人間の身勝手ではないかと訴える。考えてみれば当たり前の感情であり、だから観客は共感するのだ。
原作の「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」が刊行されたのは1968年。日本では69年に早川書房から翻訳本が出た。定価330円だった。