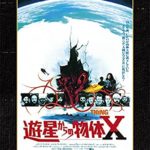若者がベトナムで人間性を失うさまを描いたキューブリックのブラックジョーク
フルメタル・ジャケット(1987年 スタンリー・キューブリック監督)
筆者は感性が鈍いので、1988年の公開当時に劇場で本作を見たとき何がいいのかよく分からなかった。新兵が鬼教官からしごきを受けてベトナムの前線に送られ、狙撃兵の攻撃を受けて右往左往するだけ。旧日本軍も顔負けの訓練の陰湿さには唖然とさせられたが、「まあ、ベトナム戦争の米国もアジア太平洋戦争の日本も同じ。違いは日本では精神注入棒のような専用器具を使っていたことくらいかな」という程度の感想だった。
数年後、本作を見返してやっとキューブリック監督の言わんとするところが少しだけ見えてきたような気がした。ベトナム戦争に対する批判。というより冷笑を交えたブラックジョークなのだと。
ベトナム戦争が泥沼化した1960年代後半。ジェームズ・T・デイヴィス(マシュー・モディーン)はアメリカ海兵隊に志願し、同年代の若者と共にサウスカロライナ州パリス・アイランドの訓練キャンプで教練を受ける。彼ら二等兵の教育を担当するのがハートマン軍曹(リー・アーメイ)。ジェームズはハートマンによって「ジョーカー」と名づけられる。
彼らは鬼軍曹のハートマンに罵倒され、平手打ちを浴びながら厳しい訓練に耐えるが、「デブ」と呼ばれるパイル(ビンセント・ドノフリオ)はいつも足手まとい。荷物の中にドーナツを隠していることがばれたため、仲間たちは連帯責任を取らされる。パイルの間抜けぶりに業を煮やした連中は就寝中の彼の体を抑えて集団で殴打。昼間はハートマンの地獄のようなしごき、夜は仲間からの仕打ちを受けて苦しむパイルは次第に精神に変化をきたしていく。その結果、卒業の夜、銃を持ってトイレにこもり、ジョーカーの目の前でハートマンを射殺。銃口を口にくわえて引き金を引き、自ら命を絶った。ここで前半が終了。
後半は海兵隊の報道員になったジョーカーがベトナムに送られる。上官の気分を害した彼は前線の取材を命じられ、同じ報道員のラフターマン(ケビン・メジャー・ハワード)と共に出発する。ジョーカーは現地で訓練所時代に一緒だったカウボーイ(アーリス・ハワード)と再会。彼が所属する小隊の一員として戦闘に参加することになる。
まもなくカウボーイの部隊は情報部から敵の後退を知らされ、その確認のためフエ市に先遣される。その過程で小隊長が砲弾を浴びて死亡。さらに分隊長がぬいぐるみを使ったブービートラップで死亡する。司令部からの命令でカウボーイが指揮を取ることになるが、進路を誤ったことに気づき、黒人兵に偵察を命じる。ところが建物に潜んだ敵兵から狙撃されて負傷。助けに行った兵士も足を撃たれてもがき苦しむ。敵の策略にはまってしまったのだ。カウボーイは兵を率いて狙撃兵の死角の位置に前進するが、自分も撃たれるのだった……。
本作で思い出すのがロバート・アルトマン監督の「M★A★S★H マッシュ」(70年)だ。朝鮮戦争(50~53年)の最前線基地で若き軍医が毎日、血まみれの負傷兵を手当しつつ、女性の上官がシャワーを浴びる姿を白日の下にさらして仲間の笑いを取るなど、戦争を楽しんでいるふうである。やりたい放題の彼らの姿にはベトナム戦争への風刺的な批判がこめられていた。だからカンヌ国際映画祭パルムドールとアカデミー賞脚色賞を受賞した。戦争なんてバカバカしいものだよというメッセージが全編に込められていた。
この「フルメタル・ジャケット」はベトナム戦争そのものを舞台にしている。前半はハートマンによる人格否定ともいえるしごきの連続。二等兵の頬を平手打ちしながら「パパの精液がシーツのシミになり、ママの割れ目に残ったカスがおまえらだ」「貴様らは人間ではない。両生動物のクソをかき集めた値打ちしかない」などと、およそ常人が考えつかない罵詈雑言を次々と浴びせかけ、浮世の垢を落とさせてお国のために働く殺人マシーンに仕立て上げる。映画の冒頭に若者たちがバリカンで頭を丸刈りにされる映像を持ってきたのは軍隊に入ったかぎりは上官には絶対服従、ベトナムで人を殺せよという教訓を表わしている。60年代は「若者の時代」といわれ、学生らは髪を伸ばし、ヒッピーと呼ばれる人々も存在した。そうした若者が坊主頭を強制され、地獄に叩き込まれたわけだ。
彼らは鬼軍曹の罵声を浴び、鬱憤を晴らすため足手まといになる仲間を集団で袋叩きにした。やられた若者は発狂。パイルは途中からハートマンに射撃の腕前を褒められるが、もはやそれしきのフォローでは復元できないほど彼の精神は破壊されていたことになる。戦争は国内にあっても人格否定の場なのだ。そういえば邦画「真空地帯」(52年、山本薩夫監督)は「兵営は条文と柵にとりまかれた一丁四方の空間にして、人間はこのなかにあって人間の要素を取り去られ兵隊になる」というテロップで終わっていた。日本と米国、映像作家たちは戦争に対して同じ違和感を覚えたのだろう。
こうした狂気が後半では銃撃の恐怖と流血の形で観客に迫ってくる。キューブリック監督はジョーカーを、胸にピースマークのバッジをつけながらみずからを「生来殺し屋」と呼ぶ「ユングの二重人格」として戦場に送り込んだ。ジョーカーは自分が米国の兵士であることを認識しながらどこか戦争への疑問を感じている。彼は一種のニヒリストであり、当時、実際にベトナムに送られた若者たちの暗喩だろう。その矛盾した精神のジョーカーの目の前で、ヘリに乗った男は機関銃を連射して野良で働くベトナムの女子供を面白半分に撃ち殺していく。まるでゲーム、娯楽だ。同乗したラフターマンが機内で乗り物酔いに苦しむさまは理性ある観客の不快感を暗示している。
報道部の上官は記事に嘘を書くことを奨励。カメラを向けられた上官は芸能人気どりのつくり笑いで写ろうとする。前線ではバイクに乗せられてきたベトナムの若い女にカネを払って性行為。アメリカナイズされたベトナム女は品をつくってモンローウォークだ。
こわもての大型機関銃の兵士アニマル・マザー(アダム・ボールドウィン)は「自由を守る戦争ではない。単なる殺しだ」と言い放つ。理性が消失したような荒くれ男こそがこの戦争の本質を見破っているという現実。彼らが椅子に座らせたベトコン兵士の死体はその主張を補強している。陳列を楽しんでいるのだ。聖戦などという大義名分はもはや前線では消し飛んだ。彼らは何かのために戦っているのではない。ただ戦争をするために戦争をしている。ベトナムは「単なる殺し」の場なのだ。
蛇足ながら
本作の原作はグスタフ・ハスフォードの小説「THE SH0RTTIMERS」。日本版は「フルメタル・ジャケット」のタイトルで角川書店から発売された。
フルメタル・ジャケットは「完全被甲弾」と訳される。本体を鉛などでコーティングした弾丸だ。劇中でパイルが語ったように直径は7・62ミリで、比較的殺傷能力が低い。
ハリウッドの刑事もの映画などで警察官が使っている銃の弾丸はソフト弾やホローポイント弾と呼ばれ、直径は9ミリ前後。発射された弾が人体に入った瞬間、内部で炸裂して飛び散り、血管や筋肉、内臓を大きく損傷する。
これに対してフルメタル・ジャケット弾はコーティングしているため体内で分裂せず、貫通つまり通り抜けていく。だから内臓などがグジャグジャになる危険性が低いわけだ。
筆者は数年前、元自衛隊員の人からこんな説明を受けた。
「戦場でソフト弾を使わず、フルメタル・ジャケット弾を使うのはハーグ陸戦条約で取り決められているから。戦闘で人体を傷つけず、苦痛を大きくしないようにという配慮。つまり敵のために痛くない武器を使いましょうというわけ。だったら初めから戦争なんかしなきゃいいのに」
彼は苦笑していた。
キューブリック監督は本作に「戦争なんか、バカバカしいからやめなさいよ」という気持ちを込めている。「およしなさいよ」と人間の愚かさを諫めていると思うのだ。
ちなみに日本公開時(88年3月)の本作の映画パンフレットには当時の文化人の賞賛コメントが掲載されていた。映画評論家の水野晴朗は「素晴らしい! これまでで最高のベトナム戦争映画」、同じく映画評論家の山根貞男は「過去のベトナム映画とは完全に一線を画し、好ましい」としている。作家の島田雅彦は「僕は流れ弾にあたったような気分だ」、嵐山光三郎は「場面から撃ち出される銃弾を思わずよけた」。今は亡き女優の山口美江もコメントし、「ベトナム戦争を鮮明に映し出した傑作」と讃えている。このパンフレットは定価400円だった。
ネタバレ注意
映画の最大のクライマックスはやはり終盤のジョーカーが属する小隊が狙撃を受ける場面だ。「危険な任務は黒人の仕事」とぼやく黒人兵が偵察を命じられて撃たれ、救援に向った味方の兵士もカラシニコフの標的にされた。負傷兵は小隊の位置に戻ろうにも戻れない。味方は敵がいると思われる建物にバカ撃ちといえるほど大量の銃弾を浴びせるが、狙撃兵には当たらず、逆に建物にあいた穴を通してカウボーイが狙い撃ちされる始末。
だが日が暮れ始めたころ、ジョーカーは敵兵が潜む建物に入り、狙撃兵の背中を目でとらえる。M16で銃撃しようとする。だが弾倉がジャムして引き金が引けない。敵が振り返る。絶体絶命。その瞬間、ラフターマンが敵を倒す。銃弾を浴びて地面にあお向けに倒れたのは女。それも少女といえるほど若い女だ。
屈強な米国の兵士を次々と撃ち殺し、怯えさせたのはたくましい男ではなく、か弱きベトナム女性だった。この拍子抜けするような設定は1975年に豊かな米国が貧しいベトコンに追い詰められたことをシニカルに象徴している。映画「ディア・ハンター」(78年、マイケル・チミノ監督)のラストで登場したサイゴン陥落。多くの日本人は75年当時、米国兵がサイゴンから脱出しようとしてヘリにすがりつき、力尽きて地面に転落するニュース映像が脳裏に刻まれているだろう。物量戦を展開した大国が野ネズミを食べて戦ってきたベトコンに敗れた現実が、本作の小柄な女性兵士に翻弄され血を流した戦いとオーバーラップする。キューブリック監督のメッセージは冷笑的だ。
重傷を負った敵の女性兵士は祈りを捧げながら、「私を撃って」と呻く。ジョーカーは悩む。目の前で苦しんでいるのは負傷兵。それも女だ。撃つのは違法行為だ。だがこれだけの深手を負ったからには助かりようもない。第一、本人が殺してくれと懇願している。長い逡巡の果てに、ジョーカーは彼女にとどめを刺す。注意して見ればわかるが、スクリーンにしっかり映し出されていた胸のピースバッジが射殺の瞬間はエリに隠れている。
かくして彼はナレーションで「私はクソ地獄にいるが、こうして生きている。もう恐れはしない」と言う。若い女を殺したからにはもう怖いものはない。やり放題やってもいいじゃないか――。こうしてハートマン軍曹と米国民が望んだ殺人マシーンが誕生した。ジョーカーを加えた男たちが銃をかまえ、煙が立ち込める戦場の暗がりを散開して進みながら合唱するのは「ミッキーマウス・マーチ」。自由を守るという正義のたわ言を真に受けて志願した男たちは、いまや子供の人気者ミッキーマウスに先導され、戦場をのし歩くのだ。これほどの皮肉があるだろうか。