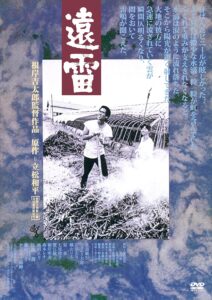あのショーンK騒動を思い出す米国青年のコンプレックスと成りすましテク
太陽がいっぱい(1960年 ルネ・クレマン監督)
米国の女流作家パトリシア・ハイスミスの小説をルネ・クレマン監督が脚本化した。モーリス・ロネとアラン・ドロンが出たフランス映画であるため、主人公ら男2人をフランス人の設定と勘違いしている人もいるが、実は米国から来た旅行者である。
米国人のトム(アラン・ドロン)はフィリップ(モーリス・ロネ)の父から「息子をフランスから連れ戻したら5000ドルを払う」との依頼を受ける。貧しい家に育ち、カネに困っている彼は報酬を目当てにフランスに渡り、フィリップと接触するが、金持ちのフィリップは帰国するが気ない。それどころかトムを常に見下し、嫌がらせを仕掛けてくる。その極めつけが恋人のマルジェ(マリー・ラフォレ)と男女のひと時を楽しむためにトムを小舟に乗せたこと。ロープが切れ、洋上を漂う小舟に取り残されたトムは太陽に焼かれて背中が水膨れ状態になる。我慢の限界に達した彼はフィリップを殺害し、彼の財産と恋人マルジェを奪うのだった。
前半のトムはフィリップにアゴでこき使われる使い走り。それでも彼の父親が約束した5000ドルが欲しいため我慢して従っている。貧乏な生まれの青年が金持ちのバカ息子にコバンザメし、フィリップはいじめっ子の心理的特性として自分を頼りにする人間を軽蔑してサディスティックにもてあそぶのだ。これではトムが殺意を抱くのも当然である。その結果、フィリップを殺害しその死体をワイヤーで縛って海に投棄する。
おまけに彼はフィリップの美しき恋人マルジェも狙っている。殺しは一石二鳥だ。こうして大胆不敵に殺しを実行するや、トムのキャラが豹変する。彼は「僕は貧乏だけど頭がいい」と言う自信家だ。物語の最初のうちはパシリの悲しさでおどおどしていたが、殺害後は持ち前の怜悧な頭脳を駆使してうまく立ち回り、刑事の訊問を堂々とかわして完全犯罪を目指すのだ。
パスポートを偽造し、スライド映写機を使ってフィリップのサインを練習。彼に成りすましてヨットの売却話を進め、銀行から1000万リラを引き出す。この大金を自分のものにせず、フィリップが生きていてマルジェに遺産として残したように工作したのち、マルジェを色仕掛けで落としてごっそりいただこうという算段だ。フィリップの友人フレディ(ビル・カーンズ)に正体を見破られた際はためらいもなく撲殺し、死体をクルマに運ぶ際、通行人と出くわすや酔っ払いを装うなど、なかなか機転が利く。マルジェとの会話に女刑事が聞き耳を立てていると気づくや、わざとフィリップの生存情報を流して捜査をかく乱する。この男、たしかに頭がいい。
パトリシア・ハイスミスの小説の原題は「The talented Mr. Ripley」。その昔、本作の紹介記事ではこれを「天才、リプレー君」と訳していた。
この作品を見るたびに思い出すのが2016年に持ち上がったショーン・マクアードル・川上(ショーンK)の騒動だ。「テンプル大で学位を取り、ハーバード・ビジネス・スクールでMBAを取得した」という触れ込みで「報道ステーション」などに出演していたが、週刊文春の報道でこの経歴が虚偽だったことが判明。父親が米国人で小学5年のときに来日したと説明していたが、実は熊本出身の川上伸一郎という純粋な日本人。高校の同級生たちも今の顔を見て彼が川上だと気づかなかった。高校時代は、ホラばかり吹くので「ホラッチョ」というニックネームだったという。
本作のトムはフィリップという身近な他人に変身したが、ショーンKは米国系日本人という自分がでっち上げた架空の人物になりすましていたわけだ。彼は15年3月から16年3月まで週に1回「報道ステーション」(テレビ朝日)に出演していた。筆者は毎週、彼の出演を見ていたが、そのコメントはまとまりも含蓄も深みも結論もなかった。毎回「これでMBA?」「なんでこんな男を使うのか?」と呆れていたほどだ。感心したのは「コンコルドの過ち」について触れたときくらいで、そんな教訓もあるのかとは思ったが、この言葉に関するショーンKの説明もはなはだ不完全だった。彼の正体がばれたあと広告会社の人に、ショーンKの出演料はいくらかと聞いたら、「はっきりは知らないけど、『報道ステーション』は1回あたり100万円以上だろう」とのことだった。嘘をついて5000万円以上を得たことになる。
英語が得意な男が顔を西洋風に作り変えて架空の人物になりすまし、日本中を騙していた。事実を伝えることが使命の報道番組まで彼を信用したとは、嘘をついたほうが悪いのか、嘘を見抜けなかったテレビ局が悪いのか。それとも両方悪いのかと、おちゃらけのひとつも言いたくなるのだ。おそらくショーンKは本作のトムのようにコンプレックスを抱いていたのだろう。上昇志向が強いわけだ。
本作の公開から61年。洋の東西を問わず、人間の愚かさは変わらない。コンプレックスは人間を成長させるが、時に自滅させるようだ。ちなみに主題歌を作曲したのはニノ・ロータ。映画音楽の歴史に燦然と輝く名曲であることは説明するまでもない。
ネタバレ注意
陰湿な嫌がらせを受けた者が復讐を果たし、美女と大金を手にする――。そういう意味で本作は一種のサクセスストーリーの要素もはらんでいる。このままでもいいじゃないか、トムの頭上に太陽の日差しを存分に振りまいてやれよとも言いたくなるが、世の中はそう甘くない。悪は滅びるのだ。
ラストは映画史に残る名場面だ。トムがフィリップを殺害したヨットに買い手がつき、陸に引き上げる際、スクリューに絡まったワイヤーに引っ張られて海中から死体が現れる。あの海の状況でスクリューにワイヤーが絡むものか、またワイヤーによってスクリューが回らないはずなのにどうやって接岸できたのかという疑念も浮かぶが、どんでん返しの衝撃にそうした疑義を真面目に考える余裕もない。前半ではヨットと小舟を結ぶロープが切れたためトムは水膨れになるほど辛い思いをし、結末はヨットとワイヤーを分離できなかったため自滅に至る。偶然なのか、それとも計算したのか、皮肉な対比となっている。
「太陽がいっぱいだ」と言いながら勝利の美酒を味わい、「最高だ」を繰り返すトムの身柄を確保するため、刑事はウェートレスに「こちらに彼を呼んでくれ」と指示する。「電話ですよ」と告げられたトムは微笑みながら画面の下手に消える。残ったのは美しい海とヨット、小島の風景。日本の映画人がこの作品を演出したら、手錠をかけて一件落着としただろうが、ルネ・クレマン監督はその後の始末を観客に想像さることで余韻が残るラストシーンに仕上げた。本作の名作たるゆえんがここにある。
トムは米国人だが、フランスの法律によって裁かれ、死刑判決は免れないだろう。73年の映画「暗黒街のふたり」(ジョゼ・ジョヴァンニ監督)で主演のアラン・ドロンがギロチンで斬首されたラストを思い出してしまう。この当時、フランスではまだギロチンによる死刑を執行していた。「暗黒街の二人」は死刑反対をにおわせる作品だった。
いっぱいの太陽を浴びたトムも断頭台の露と消える運命なのだろう。