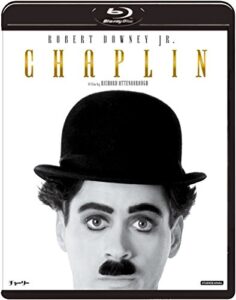多国籍の人々が互いを支え合って生きる米国版「深夜食堂」
パターソン(2016年 ジム・ジャームッシュ監督)
ジム・ジャームッシュの良さはよく分からないけど、この映画はいい。筆者は試写会で最初に見学し、その後、飯田橋ギンレイホールで上映したので見に行った。2度目のほうが感動したような気がする。
ニュージャージー州パターソン市に住むバス運転手のパターソン(アダム・ドライバー)は単調な日々を送っている。毎朝、妻のローラ(ゴルシフテ・ファラハニ)にキスして出勤。夕食後は犬の散歩に出かけ、バーでビールを飲む。趣味は詩作で一冊のノートに書きためている。甘えん坊のローラは芸術志向で家の模様替えに熱中時代だ。
本作は彼の1週間の話。これといった事件は起きないが、コミカルな味つけのため途中でやめられない。それどころか何度見ても満足。不思議だ。
自宅とバス、行きつけのバーの3カ所で物語が進行。パターソンは自作の詩をそらんじながらバスのハンドルを握り、ローラへの愛情を詠う。路上で見知らぬ少女の詩に耳を傾けることもある。この少女の詩が素晴らしい。
映画通の知人に指摘されたのだが、登場人物はマイノリティーばかりだ。ローラはイラン人、バス会社の同僚はインド人、バーのマスターは黒人。最後に出てくる詩人(永瀬正敏)は日本人だ。
多くはつましく暮らす庶民で、ローラは菓子が285個売れたからお祝いしようとはしゃぎ。パターソンに買ってもらったフォークギターで誰もが知っている曲を弾き語りする。インド人は家族のことで毎日、愚痴を連発。バーの黒人青年は失恋してヤケになり、マスターは妻のヘソクリを使い込んだのがばれて大声でどやされる。まるで米国版「深夜食堂」。実にほほ笑ましい。家の近所にこんな店があったら楽しいだろう。
パターソン市は人口15万人。主人公はここに生まれてここに育ち、おそらくこの地で死ぬのだろう。その彼を日本の詩人が預言者のように勇気づけて去っていく。詩人の相づち「ア~ハァ」が絶妙。永瀬はいい役をもらったよ。
この映画は何が面白いのか分からない。ただ、バーやバスの会話にかつてわれわれ日本人が営んでいた触れ合いが感じられるのだ。人々は主張し、ぼやき、そして悲しむ。それをパターソンとマスターが受け流し、気まぐれのように受け止めてやる。緩やかな交わりが米国流の人情であるらしい。こうして穏やかな暮らしが続いていく。久しく忘れていた人情が米国映画で蘇えるとはいささか皮肉なめぐり合わせ。感動のポイントに国境はないということか。