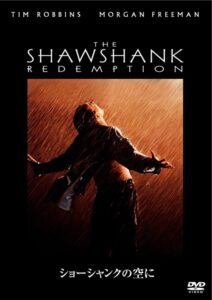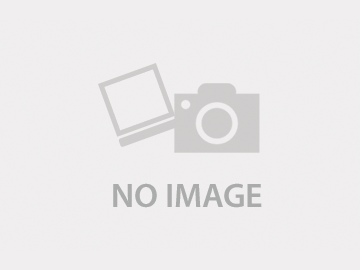大統領のご寵愛を求める男たち、憎悪と嫉妬の滑稽劇
「KCIA 南山の部長たち」(2020年 ウ・ミンホ監督)
1979年10月26日、韓国の朴正熙(パク・チョンヒ)大統領が暗殺された。当時筆者は大学生で、ついに死んだかと思った。射殺とはいかにも独裁者の末路らしいと。米国のCIAが暗殺を画策したという説も出たが、いまだにはっきりした結論は出ていない。
その謎に切り込んだがこの「KCIA 南山の部長たち」だ。劇中では仮名になっているが、殺害犯の実名は金載圭(キム・ジェギュ)で、悪名高きKCIA(大韓民国中央情報部)の部長。つまりKCIAのトップだった。KCIAの本部がソウルの南山にあったため、歴代のトップは「南山の部長」として恐れられていた。
映画は79年10月に、KCIAのキム・ギュピョン部長(イ・ビョンホン)が会食中にパク大統領(イ・ソンミン)を殺害する場面から始まる。70年代の韓国はパク大統領の絶対的な支配下にあり、KCIAは大統領直属の諜報機関として、どの政府機関よりも優位に立っていた。
事件の40日前、元KCIA部長で米国に亡命中のパク・ヨンガク(クァク・ドウォン)はコリアゲートの捜査の重要参考人として米下院議会の聴聞会に出席。パク大統領を「革命の裏切り者」として告発する。パク大統領ら韓国の政権中枢は61年のクーデターを軍事革命と認識していたのだ。パク大統領はここまで19年間にわたる長期独裁を敷いていた。
パク元部長の暴露本出版計画を知って動揺するパク大統領のために、キム部長は渡米。パク元部長を説得して原稿を受け取る。2人は友人だった。
このことで得点を稼いだが、帰国後、パク大統領の執務室を大勢の男たちが調査している姿に唖然とする。米国が盗聴器を仕掛けたというのだ。彼とことごとく敵対するクァク警護室長(イ・ヒジュン)はキム部長を「情報部長のくせに気づかなかったのか」と大統領の面前で悪しざまに罵る。
まもなくキム部長はパク元部長がフランスの韓国大使館に呼ばれていることを知る。クァク室長の手の者がキム部長の部下をこっそり操って裏工作をしたあげく、パク元部長を殺害しようとしているのだ。これに対してキム部長は配下のスパイを使って応戦。こうした行為の中、パク大統領に対し、国内のデモ隊に発砲してはならないと意見具申をして疎んじられるのだった。
出てくる男は悪人ばかり
一貫して映し出される緑色を基調とした深みのある映像、ハードボイルドタッチの乾いた演出。さらに音楽が緊迫感を高める。銃を突きつける場面もあるが、ラストまで淡々と物語が展開する。このあたりは色調を含めて米国のスパイ映画「ブリッジ・オブ・スパイ」(15年)や「クーリエ:最高機密の運び屋」(21年)を思わせる演出だ。日本の映画人はここまでクールなタッチにまとめることはできないだろう。
この映画に出てくる男は悪人ばかりだ。パク大統領を初め幹部どもはみんな国民を支配することしか考えていない。釜山でデモが起きるとパク大統領は「2、3人捕まえてデモの黒幕に仕立て上げろ」と命令。クァク室長は「デモの奴らを戦車でひき殺せ」と絶叫する。亡命したパク元部長などは現役時代に、野党幹部を逮捕して苛烈な拷問を加え、憲法改正に協力させた過去がある。
主人公のキム部長は理性的な男のようだが、参考人を事情聴取するときに周辺の取調室から漏れる拷問の悲鳴を聞かせ、「ここはKCIAだ」と威圧する。どやつもこやつも、パク大統領の側近である以上、悪の肥溜めにどっぷり染まっている。これがかつての韓国中央部の実態だ。パク大統領が「民主主義が欲しいなら、米国に行け」と言うとおり、韓国には民主主義が存在しなかったのである。深夜の街頭を戦車が走行する場面がそれを象徴している。
こうした側近たちとパクの関係は主人と飼い犬の主従関係だ。パク大統領は彼らと個別に会う際に「キミのそばには私がいる。好きなようにやれ」とうそぶく。彼ら忠犬はご主人様に気に入られるために盗聴であろうが拷問であろうが殺人であろうが、やりたい放題だ。パク大統領は彼らを競わせて、自分の地位の安泰をはかっている。ご主人様のご寵愛を求めるワンワンたちと大統領の関係はまるで喜劇。おそろしく滑稽だ。
パク大統領の死は彼のやりすぎが原因ともいえる。部下たちを意思を持たない道具として使ったためコントロールを誤った。その結果、殺害という憂き目に。独裁者には暗殺が似合っているのかもしれない。
日本の企業でもスパイごっこが
こうしたことは日本の企業でも同じだろう。経営者が社員たちに個別に「キミを信頼してる」「頼りにしてるよ」と言って、それぞれが疑い合うように誘導する。筆者は20代のころ、都内の編集プロダクションに勤務し、取材ライターとして旺文社の芸能ページを担当していた。その編プロの社長兄弟がまさにこの独裁者タイプだった。
兄弟は社内にスパイを配置。スパイは社員の動向を観察してはリポートを書いて社長兄弟に報告していた。誰と誰が酒を飲みに行ったというような話までだ。べつに社員が労働組合を作ろうとしたわけではない。その社長兄弟は社員の動きを知り、社員同士をいがみ合わせることが企業家のカッコいい姿だと信じ込んでいたのだ。ちょうどバブル時代で、社長兄弟の部屋にはいつも戦国武将のイラストを表紙にした「プレジデント」が置かれていた。筆者はこうした行為を目の当たりにしていたので、本作に描かれた人間の愚かな行動を見るにつけ、その心理がなんとなく理解できる。
パク大統領とその側近たちも、企業に巣食う経営者と子飼いのスパイたちも、支配欲のかたまりだ。本作のパク大統領は国民に尽くそうという意識はない。米国が自分を切り捨てようとしていることに気づき、その焦りを解消するようにデモ隊を武力でねじ伏せようとする。人気取りのためなら、無実の者を捕えて痛めつけようとする。まさに暴君だ。
そう考えると、本作は国民を支配していた連中の“暗殺バカ話”ともいえる。ご寵愛を失った男が精神的に追い詰められ、愛情が憎悪に転じた。言い方を変えれば、「男の嫉妬」の物語だ。ただし、このバカ話にはいまだに闇に閉ざされた朴正熙暗殺事件の謎が凝縮されている。途中、説明不足で意味がよく分からない場面もあるが、キム部長がパク大統領の側近として疎外感を感じて追い詰められていく心理描写はお見事。セリフの少ない脚本の中に事件の真相が浮かび上がる。
そして何よりも、暗殺場面は見応えがある。楽しい宴席の最中にキム部長はパク大統領を痛烈に批判し始め、そのあげく拳銃の引き金を引く。血塗られた描写に、これほど凄惨だったのかと鳥肌が立つ思いだ。スティーブン・スピルバーグ監督が「ミュンヘン」で再現した虐殺シーンに引けを取らないリアリズム。本作はラストだけでも見る価値がある。
蛇足ながら
韓国映画のすごいところは政治的暗黒時代をしっかり描く姿勢を失っていないことだ。「大統領の理髪師」(04年)、「タクシー運転手 約束は海を越えて」(18年)、「1987、ある闘いの真実」(18年)など独裁時代の悪政を描いた作品を数えだしたらきりがない。
これに対して昨今の日本映画は戦前の軍国主義を糾弾する作品が少ない。かつては「わが青春に悔なし」(46年、黒澤明監督)、「眞空地帯」(52年、山本薩夫監督)、「人間の条件」3部作(59年~、小林正樹監督)、「戦争と人間」3部作(70年~、山本薩夫監督)、「小林多喜二」(74年、今井正監督)などが軍部や翼賛政治を痛烈に批判した。「帝銀事件 死刑囚」(64年、熊井啓監督)も冤罪事件の真犯人像を731部隊に投影している点において戦前ものと分類していいい。
だが、その後は「連合艦隊」(81年、松林宗恵監督)や「君を忘れない」(95年、渡邊孝好監督)など、天皇主権の軍国主義時代を追及するよりも、観客が戦争の悲劇に酔ってしまう作品にシフトしていった。なんとも嘆かわしい。
ネタバレ注意 モデルは行方不明の金炯旭
「KCIA 南山の部長たち」に登場するパク元KCIA部長のモデルは金炯旭(キム・ヒョンウク)という人物。69年にKCIA部長を解雇されたあと、大統領選に出馬するも落選。73年に台湾ルートで米国に亡命した。本作が描いているとおり、米国で朴正熙の不正を暴露。その中には朴の金大中事件(73年8月)への関与もあったとされる。
だが金炯旭は79年にフランス・パリで行方不明になった。映画では射殺されたあと機械でミンチになったように描かれているが、その生死は不明だ。ただ、KCIAによって誘拐・殺害されたという説が濃厚である。
劇中でクァク室長がパク元部長殺害を企てるものの、キム部長の手の者が彼を横取りして連れ去る。結果的にキム部長の指示で射殺。おそらくはクァク室長に手柄を挙げさせないため、自分の指示で殺害したかったのだろう。まさに非情のライセンス。このあたりも独裁者にすがりつく飼い犬の悲劇と喜劇だろう。