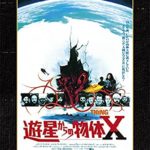老教授が出会った“家族の煩わしさ”
家族の肖像(1974年 ルキノ・ヴィスコンティ監督)
日本公開は78年11月。ロングヒットし、ヴィスコンティのブームが起きた。
ローマのアパルトマンに住む老教授(バート・ランカスター)は絵画の研究をしながら静かな生活を送っていた。ある日、その暮らしに4人の奇妙な男女が入り込んでくる。右翼の実業家の妻で若い愛人コンラッド(ヘルムート・バーガー)を持つビアンカ(シルヴァーナ・マンガーノ)とその娘リエッタ(クラウディア・マルサーニ)、それにリエッタの恋人ステファノだ。彼らは教授の上階に移り住み、大がかりな工事はするわ、食事の約束はすっぽかすわ、セックスに没頭するわとやりたい放題。そのあげくコンラッドは深夜に暴漢に襲われるのだった……。
ドラッグ、3P、不倫ときて、母娘の肉体をいただく親子ドンブリなどさまざまなタブーが盛り込まれている。右翼と左翼の対立、母と娘の不信感も忘れてはならない。オープニングのクレジットに重なる爆発めいた工事の騒音は静謐な暮らしが破壊されていくことを暗示している。
老人の平凡な日常の中に、70年代の世界的な反体制運動を構成したイデオロギーや性的な乱倫を盛り込んだ。美術を研究する学究肌の老教授と背徳的な人間たちの共生というミスマッチはこの時代の複雑で危うい世相を表している。
ヴィスコンティ監督は脳出血で半身不随になり、本作の撮影では死をも覚悟していた。教授は監督の自己投影として資本主義の物質文明を批判。コンラッドが主張する資本主義の腐敗を認め、腐敗した社会を「いっそう危険で、偽装されている」と喝破する。右翼の妻の愛人が左翼という皮肉な人間関係の中で、一見政治思想と関わりのなさそうな教授が自己の考えを吐露してコンラッドに賛同。老人は美術のほかにも真贋を見分ける目を磨いていたことになる。
こうしたコンラッドへの共感の裏にヴィスコンティ監督の同性愛へのシンパシーがあることは否定できない。だからコンラッドを失った教授は意気消沈する。
公開された74年は世界的な学生運動が退潮に向かっていた時期。コンラッドが左翼活動家として登場して右翼ファシストの殺人を追及したのは、貴族でありながらマルクス主義の影響を受けたヴィスコンティ監督のイデオロギー表現だろう。
教授は優雅な引きこもり生活から引き出され、若者世代とのあつれきを味わう。彼は困惑する。だがその一方でこの刺激を楽しんでいる。美術品に囲まれ、妻を切り捨てた過去と母の思い出に浸っていた孤高の老人は、実は心の底で家族のつながりを味わいたかった。彼が家族の煩わしさに直面する姿に、観客は「老いとは何か?」という命題を読み取り、物語の展開に呑み込まれていく。
本作は老年を意識した男性こそ見るべき映画。老いたとはいえ他人を頑迷に拒絶してはいけない。たとえ70歳、80歳になろうとも、せっかくの人生なのだから刺激的に生きたいものだ。それを可能にするのはほんの少しの冒険心。人はいくつになっても邂逅に恵まれるのだから。