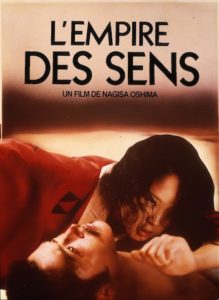クルマがボコボコになる衝撃の追跡劇
フレンチ・コネクション(1971年 ウィリアム・フリードキン監督)
思えば1970年代のウィリアム・フリードキン監督は絶好調だった。本作で第44回アカデミー賞の作品賞、監督賞、主演男優賞など5部門を受賞。その後「エクソシスト」(73年)で世界中を怖がらせ、フランス映画のリメイク版「恐怖の報酬」(77年)を発表した。
本作は60年代に起きた実話を基にしている。冒頭はフランスから始まる。麻薬の売人を張り込む現地の刑事が何者かによって射殺された。同じころ、米ニューヨークでは市警の麻薬課に所属するドイル刑事(ジーン・ハックマン)と相棒のラソー刑事(ロイ・シャイダー)が小物の売人を追いかけて逮捕。暴力をちらつかせて自白に追い込む。その夜、2人はナイトクラブで札束を切って豪遊する男女を怪しいとにらんで追跡する。この男はサル(トニー・ロー・ビアンコ)という、しがない軽食堂の経営者だ。サルは高級車で店を出ながら、途中でボロいクルマに乗り換えて自分の店に着く。この動きはますます怪しい。ドイルらは上司にサルへの盗聴許可を要請して電話を監視する。
一方、フランス・マルセイユでは知性的な風貌の実業家シャルニエ(フェルナンド・レイ)がテレビスターのアンリ(フレデリック・ド・パスカル)と悪だくみの話し合いをしたあげく、シャルニエはニューヨークに到着。アンリも映画を製作するとの名目で愛車リンカーンコンチネンタルとともに米国に入国してくる。ドイルたちはサルを尾行して高級ホテルに入るのを見届け、彼がシャルニエと接触したことを確認。サルとシャルニエが結託していることを見破り、捜査の輪を絞り込む。やがてアンリを含む密輸と売人が大量のヘロインを米国で売りさばこうとしていることにきづくのだった。
公開当時、映画誌は「全編が見せ場の連続」と絶賛した。その言葉どおり、刑事がひたすら追いかける緊迫の場面が続く。最初はサルを一晩中追いかけ、次に彼を追ってシャルニエの尾行にいたる。シャルニエは高級ホテルのレストランで食事をし、それを戸外で監視するドイルは寒風吹きすさぶ中、ハンバーガーとまずいコーヒーで暖を取る。
その後は徒歩のシャルニエをマークするのだが、この追跡の描写が緻密にできている。とくに注目なのが地下鉄のホームだ。シャルニエは電車に乗るのか、それとも降りるのか――。尾行に気づいたシャルニエはポーカーフェイスでホームに降り立ち、ドイルを巻いて逃げる。このときの「バイバイ」と手を振るしぐさがラストの捕り物に呼応しているという仕組みだ。
一番の見どころはドイルがシャルニエの身辺を警護する殺し屋に狙撃される場面。ドイルのそばを歩いていたベビーカーを押す女性が被弾して倒れる。ドイルが回転弾倉の拳銃を手にビルの屋上に上がると、そこに狙撃者の姿はなく、ライフルと弾丸が無造作に残されただけ。眼下には走って行くスナイパーの姿。あとを追うが、男は電車に飛び乗って逃走。ドイルは走ってくるクルマを借りて高架下を突っ走って追いかける。これがすごい迫力だ。
本作の前後に「ブリット」(68年)、「夜の訪問者」(70年)、「バニシング・ポイント」(71年)などカーアクションものはつくられていた。というより、クルマの暴走がブームになって「カーチェイス」という言葉が誕生、その後のアクション映画の基礎を作った。「ブリット」はスティーブ・マックイーン扮する刑事がサンフランシスコの坂道から郊外の道に抜け出して猛烈なスピードで犯人を追う。「夜の訪問者」でチャールズ・ブロンソンが対向車をよけながら疾走するのは山道だった。「バニシング・ポイント」ではバリー・ニューマンが70年型ダッジ・チャレンジャーを駆って意味もなく砂漠を突っ走った。いずれもスピード感に満ちていた。
だが、同じカーアクションでも「フレンチ・コネクション」は常軌を逸していた。高架の線路を走る電車とその下の道路を追うクルマが並走。クルマは対向車をかわし、かわしきれないときは対向車とぶつかり、ベビーカーの女性を避けるために壁にぶつかるなどひたすら衝突しながら進んでいく。当然ながら、クルマはボコボコだ。ドイルが警察手帳を見せて「クルマを貸せ」と乗り込んだとき、持ち主は「いつ返してくれる?」と聞いたが、残骸のようになった愛車を見たらショックで卒倒するだろう。
しかも電車の中では犯人が自分を追いかけてきた車掌を撃ち、運転士に拳銃を突きつけて駅で停車しないよう脅す。上と下の脅威が交差するのだ。おそらくアカデミー賞の選考委員は全編を貫く刑事たちの徒歩による尾行と仰天のカーチェイス、つまり追っかけ精神に圧倒されて本作に一票を投じたのだろう。
さらに言えば、もうひとつ見どころがある。アンリが持ち込んだリンカーンコンチネンタルだ。ドイルはこのクルマがフランスからヘロインを運んできたと見込んで押収し、警察署でバラバラに解体する。クルマは人間の手で一枚ずつ部品をはがされていく。カーチェイスでは衝突でクルマがボロボロになったが、リンカーンの場合は作業員らの手でタイヤの内部、シートの裏側、エンジンルームまで徹底的に調べられ、無残なほどバラバラに解体されてしまう。だが、どこをバラしてもヘロインは見つからない。万事休す。このときラソーがリンカーンの仕様書に記載された重量とフランスを出国したときに実測した重量が違うことに気づく。56キロの差は何を物語るのか――。リンカーンの解体は地味ながら、刑事たちの執念を思い知らされる場面だ。
刑事ドラマにしては銃撃シーンが少ないことも特徴だ。ドイルが狙撃される場面と、ラストのギャング対警官隊の撃ち合いくらい。しかも派手さはない。映画全体がドンパチよりも刑事と犯人の追っかけっこに重点を置いているのだ。
ラストはドイルがシャルニエを追って廃屋の中を進む映像。物陰に人が動いたため拳銃の全弾を浴びせたところ、同僚警官を誤殺してしまう。彼は回転弾倉に弾を込めてシャルニエを追い、一発の銃声が響く。誰が撃たれたのか不明のままジ・エンド。こうした余韻を残す結末が受け入れられた時代だった。