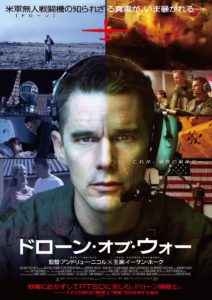ラーメンが食べたくなる究極の南極巣ごもり映画
南極料理人(2009年 沖田修一監督)
新型コロナで家に閉じこもっていたら、本作を思い出した。南極基地で働く隊員の暮らしこそ究極の巣ごもり生活。料理人の目を通して地の果てで生きる男たちを描いたコメディーだ。
舞台の「ドームふじ基地」は標高3800メートルの場所にあり、平均気温はマイナス54度。ペンギンやアザラシはおろか、ウイルスも生息できない極寒の地だ。調理担当の西村(堺雅人)は毎日工夫をこらして料理に腕をふるっている。隊員は氷雪学者の本山(生瀬勝久)や気象学者の金田(きたろう)、医師の福田(豊原功補)ら8人。それぞれが自分の仕事をしているが、これといった大事件が起きるわけではない。夜はカクテルバーを開き、麻雀に没頭。昼は雪の上で野球とそれなりにオフを楽しんでいる。
映画はこうした一般人が知らないサバイバル生活を覗かせてくれる。厳しい寒さのせいか、彼らは貪るようにおにぎりや中華料理を頬張る。その食べっぷりの良さとおいしそうな料理が本作の魅力だ。実際の隊員も食べることが一番の楽しみなのだろう。
閉ざされた暮らしへのとらえ方も人それぞれだ。海上保安庁所属の西村は交通事故で負傷した先輩の代わりとして半ば強制的に派遣された。車両担当の御子柴(古舘寛治)は自動車メーカー社員で「俺は左遷されたんだ。日本に帰りたい」と悲嘆にくれる。福田は「ここにあと2、3年いたい」と南極暮らしが気に入っている。同じ人間でも閉鎖空間への耐久性が違うのだ。それは現在の日本人も同様で、家にこもって気が滅入る人もいれば、楽しんでいる人もいるらしい。
隊員たちにはドラマもある。若い川村(高良健吾)は日本に残した恋人と遠距離恋愛中で、1分710円の電話をかけるが、会話がしっくりこない。金田は夜な夜な食堂に忍び込んでインスタントラーメンを盗み食い。食べ過ぎてもう在庫がないと知るやショックを受け、西村にラーメンをつくってくれとせがむ。「ボクの体はラーメンでできてるんだよ」というセリフはかつての川島なお美のようだ。彼のおかげで見終わったあと無性にラーメンが食べたくなる。こわもての本山は電話で妻に敬遠され、他のメンバーたちにからかわれる。その姿はいかりや長介に絡む加藤茶&志村けんさながら。こうして基地の中で緩やかな時間が流れ、全員の帰国で幕を閉じる。成田空港の風景がいい。
この映画の特長は説教くさくないことだ。「南極物語」のような悲劇性を排除し、男たちの境遇をひたすらユーモラスに表現できたのは監督が77年生まれの沖田修一だからだろう。もし団塊世代の監督だったら「とめてくれるなおっかさん」とばかり人情話に走り、大好きな根性論をちりばめて「お国のために命を捧げるのだ」と役者たちを慟哭させただろう。
ただ、西村が食べながら泣く場面は必要なかったと思う。いきなり湿っぽくなるのだ。やはり日本の観客は涙を見ないと満足できないのか。