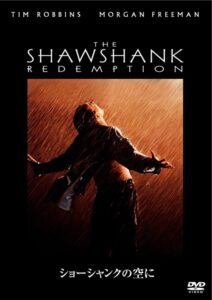娘を凌辱・殺害されたキリスト者、報復の苦しみ
「処女の泉」 (1960年 イングマール・ベルイマン監督)
映画「わが母の記」(2012年)で役所広司扮する作家の井上靖が「映画『処女の泉』を見た」と言う娘に対して、「ピンク映画などを見に行きおって!」と一喝するシーンがある。「処女の泉」を愛する観客はさぞかし笑ったことだろう。
本作の舞台は中世のスウェーデン。裕福な地主テーレ(マックス・フォン・シドー)は娘のカリン(ビルギッタ・ペテルソン)に教会への届け物を命じる。カリンは馬で出かけるが、同行した女奉公人のインゲリ(グンネル・リンドブロム)は恵まれた境遇のカリンを心の底で憎んでいる。
教会への道すがら、カリンは貧しい羊飼いの3兄弟に出会い、食事を分け与える。だが兄弟はカリンを陵辱した上に殺害。インゲリはカリンを助けたい気持ちはあるが、何もしない。
3兄弟は偶然にもカリンの家を訪ね、そこが自分たちが手にかけた少女の家だと知らず、食事と宿を施してもらう。テーレは彼らが持っていた衣服から、娘が殺害されたことに気づいて兄弟と激闘。激情にかられて、幼い弟まで殺害する。その後、インゲリの案内で山に登り、山中で変わり果てた娘と対面する。嘆き悲しむテーレの前でカリンの亡骸のそばの地表から水が噴き出し、みるみるうちに泉となるのだった。
筆者は四0年ほど前、早稲田松竹のリバイバル公開で久しぶりに見た。年ごろの娘を持つ身としては、テーレへの同情で胸がふさがれる思いがする。悪漢どもを殺しても娘が生き返るわけではないが、復讐を遂げる姿に「よくやった」と声をかけたくなる。
その一方で、敬虔なキリスト教徒のテーレが3兄弟殺害を自分のおかした罪として嘆き、「罪滅ぼしのためにここに教会を建てる」と神に誓う言葉も感動的で。これが日本映画なら復讐を果たして一件落着となるだろうが、「復讐するは我にあり」の教えを胸に刻み込んでいる人たちはさらに深奥なる苦悩を味わうのだろう。宗教が人に与える哲学の違いが現れている。
物語は心優しい少女が困った人に同情して施しを与えたところ、兄弟が空腹を満たすと同時に野獣の本能をむき出しにして傷つけたというもの。身分の低い女が高貴な少女の受難を手をこまねいて傍観する要素を含めて、エゴイズムに満ちている。人間が太古の昔から直面してきた不条理な悲劇だ。少女レイプという重大性から、日本公開当時は暴行シーンがカットされたという。
ちなみに本作を撮った当時、監督のイングマール・ベルイマンは42歳だった。