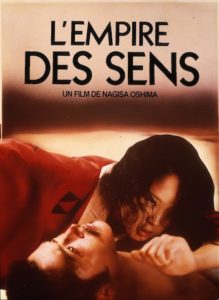血みどろの切腹は必要だったのか?
最後の忠臣蔵(2010年 杉田成道監督)
日本人は忠臣蔵が好きだ。そこには日本人が信奉してきた「忠君孝心」の精神があるのかもしれない。身分の高い存在を自らつくり出し、神のように尊崇するのだ。そして命がけで主君の命を守る。あるいは主君の名誉を守る。昔風に言えば「天皇陛下のおんために命がけで戦う」ということ。忠臣蔵の場合は「君辱めらるれば、臣死す」だろう。なんとも威勢のいい言葉である。
本作は忠臣蔵をモデルにしている。ただ、殿中松の廊下の刃傷も本所松坂町の吉良邸討ち入りもない。その後の忠臣蔵である。生き残った赤穂の下級武士の物語。池宮彰一郎の小説を映画化した。なかなか面白い。製作本数が少ない時代劇を手かけたことは評価できる。だけど注文をつけたくなる。そんな作品だ。
討ち入りから16年。討ち入りの夜、吉良邸にいながら、一人だけその場を離れて生き残った寺坂吉右衛門は諸国をめぐり、切腹した赤穂武士の遺族を訪ねて大石が託した銭を渡す旅を続けていた。その最中、吉右衛門は討ち入りの前日に逃亡した瀬尾孫左衛門(役所広司)を見かける。吉右衛門は孫左衛門がなぜ吉良邸から蓄電したのかをずっと疑問に感じていた。そのことを問いただそうとしたが、孫左衛門を見失ってしまった。
実は大石内蔵助の使用人だった孫左衛門は大石の娘の可音(かね・桜庭ななみ)と暮らしていた。彼は討ち入り前に大石から「わが子を頼む」と命じられて逐電、以来、可音を守ってきたのだ。可音をわが娘のようにかわいがり、行儀作法から読み書き、芸事の素養まで身につけさせた。
ある日、人形浄瑠璃を見物した可音は豪商・茶屋四郎次郎(笈田ヨシ)の息子・修一郎(山本耕史)に見初められる。さらに偶然にも四郎次郎から息子が胸に抱いている「謎の姫御料を探してくれ」と依頼される。姫御料の素性は自分が育ててきた可音なのだ。
可音の婚儀はめだたいが、問題があった。嫁入りさせるには大石の忘れ形見だという秘密を明かさなければならない。また、可音が孫左衛門に恋心を抱いていることも悩みのたねである。そんな中、吉右衛門に可音の存在を知られ、孫左衛門は刀を抜いて追い払う。やがて可音は婚礼を承諾し、茶屋家に向かうのだった……。
作品から漂うのは武士道の隷従的な忠義心よりも人の使命感だ。孫左衛門は敬愛する大石の忘れ形見を命がけで守ろうとし、暮らしの世話になっている親しい者たちにも自分と可音の素性を明かさず、ひっそりと暮らしている。可音を守るために、仲の良かった吉右衛門さえ斬ろうとする。前半はこうした地味な忍耐の描写が続くが、忠臣蔵を土台にしているため見応えがある。
ただ、孫左衛門と可音の関係は不自然でもある。可音にとって乳児ころから育ててくれた孫左衛門は実父も同然だ。恋心を抱くことはあり得ない。「曽根崎心中」の映像を使うために無理をしたのだろうか。
見どころは可音の輿入れだ。可音は孫左衛門のために自ら縫った着物を贈り、「幼きときのように抱いてほしい」と言い、孫左衛門の胸ではらはらと涙を流す。可音を駕籠に乗せた嫁入りの行列は、最初は夜の山道を孫左衛門一人が付き添う寂しい風情。見ている観客もかわいそうだなと同情してしまうが、まもなく松明を手にした吉右衛門が大勢の従者とともに加わってほっとさせられる。さらに旧浅野家の家臣が続々と参加。嫁入りの行列は頼もしさを増していく。浅野内匠頭の乱心から討ち入り、浪士の切腹と続いた血生臭い物語を美しい映像が清めた。
蛇足ながら
それだけにラストは疑問が残る。杉田監督は切腹マニアなのか、それとも「ハラキリ」好きの外国人に受けようとしたのか、派手な切腹を披露。吉右衛門が見守る中、孫左衛門は大石の位牌の前で腹を切り、介錯を断って首を切って果てる。これは妙だ。
日本には穢れと清め、ハレとケという概念があり、その伝で考えれば、孫左衛門は婚礼という晴れの日を血穢(けつえ)で汚したことになる。たしかに池宮の原作には「鮮血が飛沫(しぶい)た。その血を浴びて二つの位牌が真赤に濡れた」とある。だが、原作に忠実に従ってここまで血生臭い映像に仕上げる必要があったのだろうか。切腹なしに完結してもよかったし、もし原作者サイドから「ハラキリを入れろ」との縛りがあったしたら、一瞬の映像を音楽で包み込んで観客にイメージさせるような方法もあったはずだ。作品に流れる養父と娘の情愛、婚礼の夜の旧臣の温かい心情などが血で穢された印象を受けるのは筆者だけだろうか。
そもそも孫左衛門は晩年、赤穂に戻り、剃髪して「休真」と号したといわれる。切腹したという説はない。吉右衛門もしかり。晩年は江戸の曹渓寺に身を寄せたとされる。曹渓寺は現在も港区内に存在し、われわれは吉右衛門の墓所を見学することができる。2人とも天寿をまっとうしたわけだ。
考えてみると、日本人は時代劇に派手な死に方を期待しがちだ。四方八方から切り刻まれて血まみれになり、悶絶しながら息絶える光景をよく目にする。こうした血を求める習性が孫左衛門の最期の描写を生んだのなら、われわれ時代劇ファンの責任は重い。