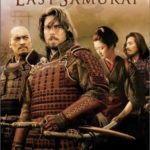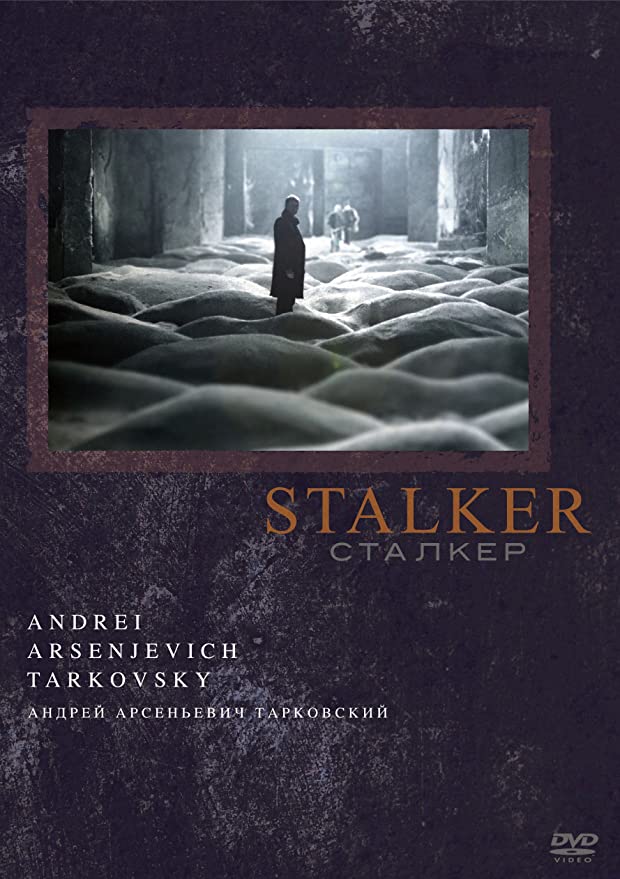
脳を侵食する理解不可能の不条理劇
ストーカー(1979年 アンドレイ・タルコフスキー監督)
ストーカーといっても女につきまとうイカレ野郎ではない。この映画では案内人のことだ。筆者は大学生のころ、ゼミの先輩に本作の話を聞いて無性に見たくなり、劇場に足を向けた。先輩の「難しい映画だぞ」という忠告どおり、理解不可能だった。だがそれでも満足感があった。
隕石の落下か宇宙人の歴訪か、「ゾーン」と呼ばれる地域がある。かつて政府が軍隊を派遣したが全滅させられ、立ち入り禁止となった。このゾーンに入りたがる人々をこっそり案内する職業をストーカーと呼ぶ。
主要人物はストーカーと作家、教授の3人。彼らは警備兵の銃弾をかわしながらゾーンに足を踏み入れる。目的は願いがかなうといわれる「部屋」だ。
一種のSF映画だが、特撮めいた映像はない。苔にまみれた戦車の残骸、気がめいる曇天、ぬかるんだ地表、ヘドロ状の地下水などの映像が流れては消える。だがタルコフスキー監督特有の水と霧の表現とあいまって、その映像は神秘的で美しい。だから2時間41分の長尺ながら退屈しない。
ストーカーは長い包帯を巻いたナットを前方に放り投げ、安全を確認しながら原野を進む。「部屋」がある建物は目の前だが、回り道をして接近。なぜならゾーンは人間の心を反映するワナのシステムであり、不用意に近づく者を殺すからだ。
観客はゾーンとは何か、「部屋」には何が待つのかとの疑問と格闘しつつ、3人が繰り広げる議論に幻惑される。宗教、科学、文学に関する言葉のいずれもが切れ切れで、ゾーンの正体が不明な以上、その主張は曖昧に響く。この不条理劇を「よく理解できた」と言う人がいたら、そいつは裸の王様だろう。
ただ、ストーカーの師匠は「部屋」から生還した途端、大金持ちになったが自殺したという。理由は死んだ弟の復活のために「部屋」に入りながら、実は富を願った自分に失望したから。「部屋」は人間の欲望をむき出しにする鏡なのだ。
ストーカーがゾーンから戻ると、彼の幼い娘は特殊な能力を身につけていた。ゾーンも「部屋」も娘の能力も何が何だか分からない。とってもシュール。だけど面白い。最初よりも2回目、2回目よりも3回目と見れば見るほどハマってしまう。タルコフスキー監督の難解さは麻薬のように脳を侵食するのだ。